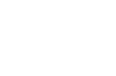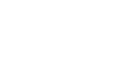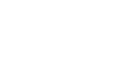9月になりました(なってしまいました)。これから入試本番までお子さまが模試を受ける機会が多くなり、模試の判定で、お子さまは自信が揺らいだり逆に油断してしまったりするかもしれません。
でも保護者のかたは判定に一喜一憂せずサポートしていきましょう。
今回は「進研ゼミ」の進路情報センター長に、模試の結果に振り回されない、模試の受け方を聞いていきます!
お子さまに戦略があれば判定は気にしなくてOK!
編集M いやあ、うちの子の夏前の模試が戻ってきましたよ。第1志望としていた大学が、あるあるのE判定!(この記事ネタとしては美味しいのですが)
多くのゼミ先輩の「E判定からの逆転合格」した実例を知っている身としては、まだ判定など気にしないで弱点攻略していけばよい!とわかっているつもりですが...が...。E判定ってやはり衝撃ですね。意外と息子もヘコんでました。9月以降、受験生は模試シーズンに突入ですし、効果的な受け方や判定のとらえ方など公私ともに教えていただきたいと思っております!
編集I 同感です。特に今年はコロナの影響でこれからの模試が本当の実力判定という気がしています。
また、大学受験講座を受講されている会員の保護者のかたのアンケートからも、子どもの実力がわからない、これからどのように模試の結果をとらえていけばよい?という不安の声も多く聞いています。
センター長 そうですね。今の段階の模試の結果については、お子さまが自分で合格までの戦略を立てて着々と勉強を進めているのなら安心! としましょう。
編集M ...ちなみにどんな戦略ならOKなのでしょう?
センター長 大事なのは、これからの受験勉強について優先順位を決めて、自分で計画的に進めていくことができるか。志望大の合格基準に対して自分の強み弱みを知って学習計画が立てられているか、です。
秋からの受験勉強として優先度が高いのは、
1位 苦手×配点の高い科目
2位 次に配点の高い科目
3位 残りの科目
となります。
センター長 それぞれ「いつまでに」「どの状態まで」もっていくかの自分の戦略があり、それに沿って勉強が進んでいている限り、模試の相対的な判定に振り回される必要はありません。むしろ結果から攻略すべき学習内容を見つけてほしいですね。
編集M なるほど〜。優先度といえば、うちの子の場合は、前回の模試で理系でありながら理科が不調だったらしいので、苦手×配点の高い理科が最優先、2位が配点の高い英語・数学 3位が共通テストで頑張らなければならない国語 地歴って感じですね。
センター長 ええ。そのようにお子さまが優先順位を決めて戦略的に勉強を進めているなら、日頃の受験勉強の成果チェックや弱点発見のための、合否判定のみではない模試の有効活用をしていただければと思います。
秋からの模試は月1ペースが受験生のセオリー
編集I 今後はどんなペースで模試を受けるとよいですか?
センター長 9月以降は例年通り月1ペースで模試を受けていくのがオススメです。ただし受けたことで安心したり、判定をみて「上がった!」「下がった!」で終わりじゃ、受ける意味はあまりないですね。
編集M たしかに。息子はE判定にビビってしまったのか、「実力がつくまで模試は受けない」と言い出してますが...。本人が納得する実力がつくまで模試を受けなくても大丈夫でしょうか?
センター長 「それは、もったいない」と個人的には思います。模試を受けている時間も受験勉強です。模試というのは、受験の予行練習。受けている時間は、本気で問題に取り組むので、終わってから理解不足に気づき、「それで間違っていたんだ!」と学習を振り返るよい機会だと思いますよ。
志望大変更を考えるタイミングはいつ?
編集M ちなみに先ほどから判定に振り回されずにというお話もされていますが、いつまで判定を気にする必要がないのでしょうか?
本当の志望大っていつまでに決めればよいのでしょう?
センター長 理想を言えば、共通テスト受験後まで志望大を変更しなくて大丈夫です。でも、その前にお子さまが模試の志望大判定結果を見てとても無理だと思い、「志望大を変えたい」と言ってくる可能性はありますね。
編集I たしかに。EやD判定が続いたら...。保護者としてもそうかな、と思ってみたり。
センター長 そんなときの保護者の役割は話をじっくり聞き、「まだいけるのではないか」と信じて励ましてあげることなのです。
編集M つい「やっぱり第1志望はあきらめたら?」...なんて言っちゃうのは、もちろんダメですよね。(言いそう...)気をつけたいと思います。
編集I でも、信じて応援するつもりで「あきらめちゃダメ」と強要するのもよくないですよね。
センター長 それはそうですね。自主性が大事です。ただ、お子さまが本当はその志望大に行きたいし、せっかく勉強も自分が考えている通りに進めているのに、判定だけで弱気になっているなら、やはり最後まで成績は伸びると信じて、保護者の方にモチベーションをあげていただきたいと思いますね。
「3教科に絞りたい!」と言ってきたときの注意点
編集I ところで子どもが「第1志望の国公立大をあきらめて、私立専願で3教科に絞りたい!」なんて言い出した時は、どうアドバイスしたらよいですか?
センター長 3教科に絞る時は、「安易な逃げ」ではないことを確認したいですね。今後受験までどのように勉強するつもりか、プランを聞いてみましょう。(志望大を変更するときも同じですよ)
編集M 受験の科目数を減らすということは、より厳しくなることがわかっているかの確認ですよね?
センター長 ええ、国公立大は無理とお子さまが自分で判断し、次に本気で行きたい私立大に向けてやる気の方向をうまく切り替えているなら大丈夫です。
ですが単に「3教科はラクだから」という理由で逃げてしまった場合、他に本気で挑んでいる高校生との勝負の中で、結果に結びつかないことが多いのも事実です。
編集I&M わかる気がします...
センター長 3教科に絞るとそれだけ各科目のレベルは上がるので、その対策は必要となります。「残りの期間でこの科目をこれだけ勉強してここまで上げる」などのお子さまの目算がないと危ないです。
編集I なるほど、科目数を絞ればそれだけ高いレベルの戦いになるということを覚えておきます!
逆に科目数が多いと苦手科目を得意科目でカバーしやすい、というメリットもありますよね。
センター長 ええ。それに今年はコロナの影響で「発展的な問題を出さない」と宣言している大学も多くなっています。今から3教科に絞る必要があるのかどうか?基礎基本を固めれば合格ラインにまだ間に合うのではないか?という提案もお子さまにできるかもしれませんね。
ぜひ、保護者のかたもお子さまの志望大の入試情報の確認をしてサポートしていただきたいと思います。
まとめ
模試は合否判定チェックではなく、模試後に発見された弱点を確実に攻略して次の模試までに学力を伸ばす確認テストと、とらえた方がよいかもしれません。
そして、お子さまはすでにそれをわかっているかもしれません。
でも実際に悪い判定が出ると、不安で勉強が手につかなくなったり、逆に良い判定で油断してしまったりすることもありますよね。
そんなときはお子さまが今、不安に感じていることとを聞いて、お子さま自身が次にすることに気づくような声掛けを、ぜひしてあげてください。