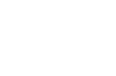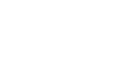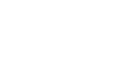大学選びでは、将来やってみたいこと、興味がある職業・仕事など『将来なりたい自分』から逆算して、志望大・学部・学科を決めることが大切です。
志望大などが明確になることで、勉強のモチベーションアップにもつながります。
しかし、将来を決める大切な選択であるために、なかなか決められなかったり、迷いや不安を感じたりするお子さまも多くいらっしゃいます。
そこで、次の4つのケースで、お子さまにどんな声かけをすれば進路選択の幅を広げられるのか、保護者のサポート術を紹介します。
①志望する学部・学科がない
②テレビ・ネットで見た〇〇の仕事が面白そう!
③憧れてはいるけれど、苦手があるから、この進路は不安...
④そもそもどんな大学があるのかわからない
ポイントは、「まず」と「それから」という2つの声かけです。お子さまの気持ちに寄りそいながら、新しい視点で考えるきっかけを与えてあげましょう。
ケース①「志望する学部・学科がない!」
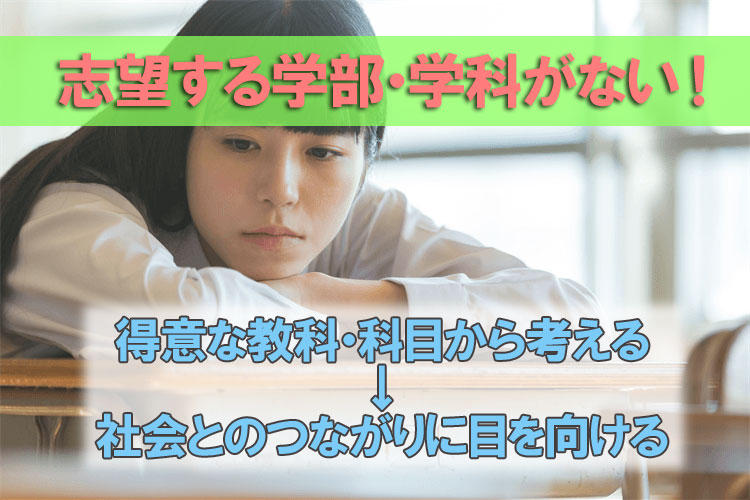
【まず】
得意な教科・科目から学部・学科を考えさせる
【それから】
社会とのつながりに目を向けさせる
【まず】得意な教科・科目から学部・学科を考えさせる
『将来なりたい自分』が決まっておらず、志望学部・学科も決まっていないというお子さまには、きっかけ作りをしてあげることが大切です。
考えやすい視点として、自分の得意な教科・科目から進路を考えるよう提案してみましょう。
「物理が得意だから理学部」
「英語が得意だから国際系学部」
「公民が得意だから法学部」
など、単純な理由でも学部・学科を考えるきっかけになるので、悩んでいるお子さまにも提案しやすいです。
【それから】社会とのつながりに目を向けさせる
大切なのは、そのきっかけ作りから進んで、将来への考えを深めていくことです。
その学部ではどんなことが学べる?
↓
そこで学んだことは、社会のどんな事柄と結びついている?
↓
学んだことを社会でどう生かせる?
これがひいては『将来なりたい自分』へとつながっていくことになります。
大学のホームページなどで情報収集をしながら、その学部に興味がわかなければ別の学部を調べ、興味のある学部を探しましょう。
ケース②「テレビやネットで見た〇〇の仕事が面白そう!」
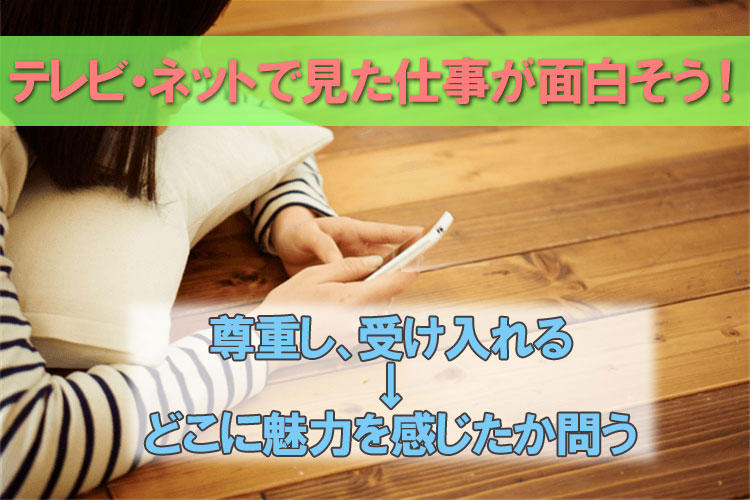
【まず】
お子さまの志望を尊重し、受け入れる
【それから】
どこに魅力を感じたかを問い、視野を広げる
【まず】お子さまの志望を尊重し、受け入れる
テレビやインターネットで見たと聞くと、「安易だ」とか「いいかげんな理由」と頭ごなしに否定しがちになりますが、そのような対応をすれば「親に話しても無駄だ」と心を閉ざしてしまいかねません。
単純な理由だったとしても、「興味を持った・きっかけ」を作ったことが大切なので、まずは受け入れてあげましょう。
【それから】どこに魅力を感じたかを問い、視野を広げる
お子さま自身できっかけ作りをすることはできているので、そこから一歩進んで考えを深めていきます。
興味を持った仕事に対して、「どこに魅力を感じているの?」と聞き、仕事に期待するやりがいを言語化させましょう。
そうすることで、その仕事に直接つながる学問、やりがいにつながる学問、または 同じような職業は何か考えることができます。
その際、保護者が自身の社会経験や仕事について語れば、お子さまにとって「働くこと」の価値、社会とのつながりを幅広く考える機会となります。
大学での学びが将来の仕事、社会とのつながりに結びつくことを意識させることで、『将来なりたい自分』が見えてきます
ケース③「憧れてはいるけれど、苦手があるから、この進路は不安...」
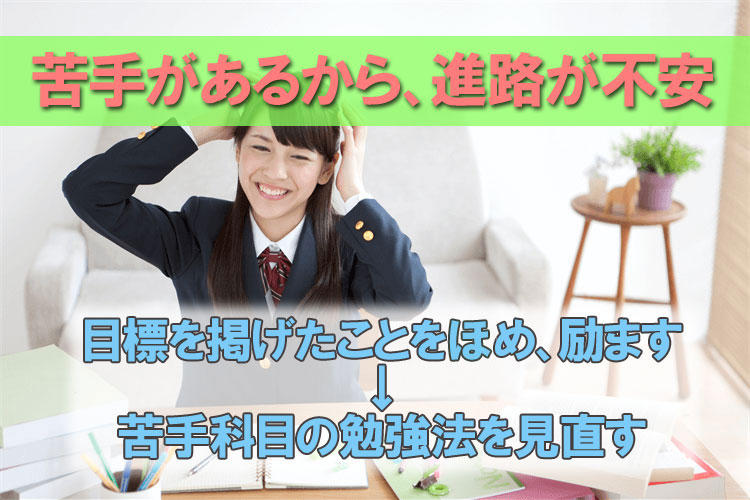
【まず】
目標を掲げたことをほめ、励ます
【それから】
苦手科目の勉強法が適切かを、本気で考えさせる
【まず】目標を掲げたことをほめ、励ます
進路選択・受験科目で、気持ちが揺らぐ大きな壁となるのが苦手科目の存在です。
『将来なりたい自分』はあるけど、そこに立ちはだかる苦手科目という不安を払拭させる・克服させるのが、このケースでのポイントになります。
苦手科目の克服や成績アップは、高1・2なら十分可能です。また、もともと高得点が取れている得意科目の得点をさらに伸ばすことよりも、得点が低い苦手科目の得点を伸ばすほうが、実は簡単なのです。
このように不安を払拭させたり、希望を持たせてあげたりすることで、お子さまを励ましてあげましょう。
【それから】苦手科目の勉強法が適切かを、本気で考えさせる
そのうえで、自分の勉強法が合っているかを学校の先生に聞いてみるようにすすめてみましょう。
進研ゼミでは、会員向けの以下のサービスも提供しています。各大学の先輩チューターに悩みを相談できたり、各教科専任のアドバイザーにアドバイスを求めたりできます。ぜひお子さまに活用するようお声がけください。
苦手科目がありながらもその進路を目指すのは、大きなやりがいを予感しているからです。『志望理由』を聞いて、保護者と話すことで、進路に対する気持ちが強くなり、それが勉強への意欲を高めることになるのです。
ケース④「そもそもどんな大学があるのか、わからない!」

【まず】
名前を聞いたことがある大学から調べさせる
【それから】
オープンキャンパスに行けない今年はWebでの情報収集を
【まず】名前を聞いたことがある大学から調べさせる
進路志望調査などがあると、お子さまが「大学名が書けない」と困ってしまうことがあります。
このようなときは、知っている大学名を挙げさせ、その大学についてインターネットなどで一緒に調べてみましょう。
こうして大学調べをすることが、志望大を決めるきっかけになります。
【それから】オープンキャンパスに行けない今年はWebでの情報収集を
多くの合格者が進路を決めるきっかけになったと語るのは、オープンキャンパスへの参加です。実際に大学を見ることで、憧れが一気に強くなります。
しかし、現状のコロナ禍では実際に大学見学に行ける機会がほとんどなくなっています。そこで活用してほしいのが、Webでの情報収集となります。
今ではWebで知ることのできる情報量の多さは想像以上ですが、それを活用できるかどうかがポイントです。
意外な方法を使ってWebでの情報収集を進めた進研ゼミの先輩たちの体験談も紹介しているので、ぜひご活用ください。
\あわせて読みたい/
また、このコロナ禍に対応し、大学でもWebオープンキャンパスを実施するなど、Webでの情報発信に力を入れています。
積極的にWebでの情報収集を進め、家庭の中で大学について語り合う機会をつくることが大切です。
4つのケースをもとに、お子さまへの声かけをご紹介しました。『きっかけ作り』と『一歩進んで考える』、この2つを意識することで、今回紹介した以外のケースにも応用できるので、お子さまの進路決定のお手伝いをしてあげてください。
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。